|
 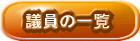 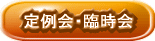    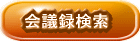 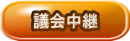
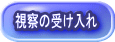 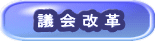 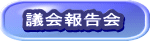 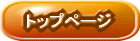
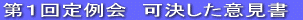
平成18年第1回定例会では,次の意見書を可決し,関係行政機関などへ送付しました。
さらなる総合的な少子化対策を求める意見書
2005年版「少子化社会白書」は,04年の合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子どもの平均数)が1.28と過去最低を更新したことを踏まえ,わが国を初めて「超少子化国」と位置付けました。予想を上回る少子化の進行によって,これまでの予測よりも一年早く,今年には「人口減少社会」に転じる可能性があると指摘しています。これまでも様々な少子化対策が講じられてきましたが,依然として少子化傾向に歯止めがかかっておらず,これまでの施策を検証するとともに,効果的な支援策について更なる検討が必要です。
その上で,少子化対策は,単に少子化への歯止めをかけることだけを目的とするのではなく,すべての子どもたちが「生まれてきてよかった」と心から思える社会,子どもたちの瞳が生き生きと輝く社会を実現する視点が重要であります。子育ては,今や,地域や社会全体が取り組む課題であり,わが国の将来を担う子どもたちの健やかな成長のために,社会全体で子育てをサポートする体制を充実することが必要です。子育てへの経済的支援のほか,地域や社会における子育てのための環境整備,働き方を見直す社会の構造改革など,総合的に子育て支援策を展開するべきです。
よって政府においては,さらなる総合的な少子化対策として次のような施策を講じるよう,強く求めます。
記
1.抜本的な児童手当の拡充
2.出産費用等の負担の軽減
3.子育て世帯向けの住宅支援
4.子どもを預けやすい保育システムへの転換
5.放課後児童健全育成事業等の充実
6.仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)が図れる働き方の見直し
送付先 内閣総理大臣・厚生労働大臣・衆議院議長・参議院議長
|
石岡第一高等学校の名称の存続についての意見書
平素は,当市の教育行政の進展のため,多大なるご支援を賜り心からお礼申し上げます。
当市は,昨年10月に石岡市と八郷町が合併し,新生石岡市として新たなスタートを切ったところでございます。さて,この度,茨城県教育委員会におきまして,県立高校の再編整備について後期実施計画が決定され,当市の八郷高等学校が対象であるということで大変驚いているところでございます。
八郷高等学校は,昭和32年石岡第一高等学校の八郷分校として開校し,昭和38年からは現在の体制となり,地元の教育機関の要衝として,地域の発展に大いに寄与してきたところでございます。
そのような状況のもと,石岡第一高等学校へ八郷高等学校が統合されることに伴い,現在の石岡第一高等学校が新たな名称になるのではと危惧を抱いているところでございます。
石岡第一高等学校は,明治43年4月16日に新治郡農学校として開校し,昭和24年茨城県立石岡第一高等学校として改称し,創立96年を迎えたところでございます。現在まで,2万人以上の卒業者を輩出し,行政,教育,芸術,地域のリーダーなど広い分野でその活躍が見られ,将来を担う生徒たちにとって核となる存在でございます。そのような歴史と伝統がある石岡第一高等学校の名称がなくなることは,地域にとって失うものも大きく,石岡市のナンバースクールとしてその名称の存続を強く望むものでございます。
送付先 茨城県知事・茨城県教育委員長・茨城県教育長
|
戻る 議会トップページへ
|

